
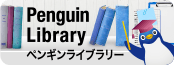
ペンギン百科、水族館レポート、施設検索などペンギン情報が盛りだくさん!

タイムマシンでひとっ飛び!ホシザキのルーツを体感しよう
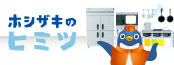
どうやって氷をつくる?食器を洗う?ホシザキのヒミツを大公開!
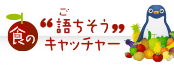
野菜や果物をキャッチ!ゲームで遊びながら食のコトバを学ぼう。
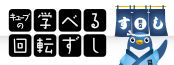
サカナのこと、どれぐらい知ってる?お寿司ネタをキューブがとことん解説!
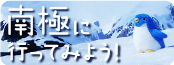
キューブの仲間、アデリーペンギンが住んでる南極ってどんなところ?

毎月かえて楽しめる!キューブのオリジナル壁紙をダウンロードしよう
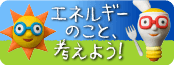
動物や植物はどうやってエネルギーをとったり使ったりしているのかな?
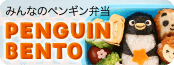
明日のお弁当はこれでキマリ!キュートなペンギン弁当の作り方はここ

辛いものの代表選手トウガラシに密着取材!「辛さ」の秘密、わかったぞ!

なっとうやミソ、しょうゆ。食卓を支える菌パワーのナゾにせまる!
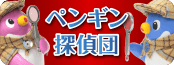
探し物ゲームで遊ぼう!よぉーく見れば答えがみつかるぞ!

食の生産から加工・流通まで、6次産業のことがわかる番組いろいろ!
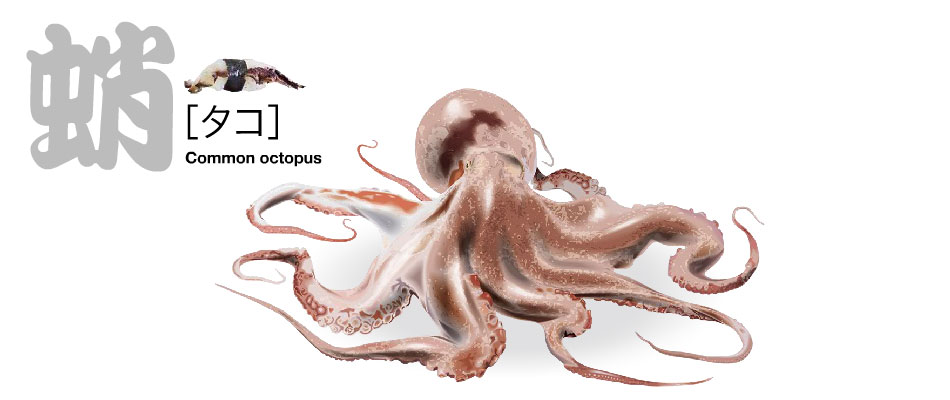
一般に、タコといえばマダコのこと。その奇怪(きかい)な姿ゆえ、海外では「デビルフィッシュ(悪魔の魚)」ともよばれます。悪魔だけに、スミで敵の目をくらましたり、まわりの地形に応じてからだの色を変えたりするのはお手のもの。敵に「腕」をかみ切られてもまた生えてくるという特異体質も、「不死」の悪魔イメージに重なります。もっとも、そんなタコを好んで食べる日本人こそ悪魔だ、とタコたちは言うにちがいありませんが。
兵庫県明石市と淡路島(あわじしま)とを隔(へだ)てる明石海峡(かいきょう)は、日本有数の水産物の宝庫。なかでも「明石ダコ」は「明石ダイ」とともに明石を代表するブランド水産物として有名です。タコの好物のエビやカニが豊富なので、これを食べることで味がよくなり、また激しい潮流にもまれることで身もしまるのだとか。ふだんはなかなかお目にかかれない「明石ブランド」の極上ダコ、一度は味わってみたいものです。
同じように見えてちがうタコとイカのスミ。どちらも敵の目をくらませる役目をしますが、イカのスミはねばり気が強いのではいたスミが黒い固まりとなり、もう一匹いるように見せかけるのに対し、タコのスミは水っぽいため周りに広がり、煙幕(えんまく)となります。イカスミはねばりがあるので食材にからみやすく、うまみ成分のアミノ酸がタコスミの約30倍あるため、イカスミの方が料理向きだとか。また、タコのスミ袋は取り出しにくい場所にあって量も少ないため、食材にするのは難しいようです。
ロープをつけた壺を海底にしずめ、タコが入りこんだところを引き上げる「タコ壺漁」は、穴を好むタコの仲間の習性を利用したもの。この習性は遠く弥生時代から知られていたようで、「タコ壺漁」に使用されたと思われる壺が弥生時代の遺跡から見つかっています。「タコ壺漁」はいまも現役の漁法ですから、すでに二千年以上もの間、タコたちは日本人の「思うツボ」にはまり続けていることになります。