
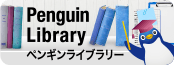
ペンギン百科、水族館レポート、施設検索などペンギン情報が盛りだくさん!

タイムマシンでひとっ飛び!ホシザキのルーツを体感しよう
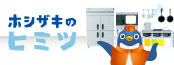
どうやって氷をつくる?食器を洗う?ホシザキのヒミツを大公開!
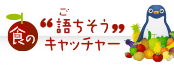
野菜や果物をキャッチ!ゲームで遊びながら食のコトバを学ぼう。
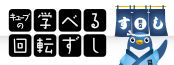
サカナのこと、どれぐらい知ってる?お寿司ネタをキューブがとことん解説!
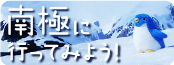
キューブの仲間、アデリーペンギンが住んでる南極ってどんなところ?

毎月かえて楽しめる!キューブのオリジナル壁紙をダウンロードしよう
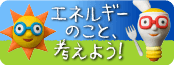
動物や植物はどうやってエネルギーをとったり使ったりしているのかな?
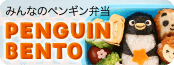
明日のお弁当はこれでキマリ!キュートなペンギン弁当の作り方はここ

辛いものの代表選手トウガラシに密着取材!「辛さ」の秘密、わかったぞ!

なっとうやミソ、しょうゆ。食卓を支える菌パワーのナゾにせまる!
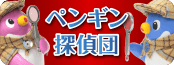
探し物ゲームで遊ぼう!よぉーく見れば答えがみつかるぞ!

食の生産から加工・流通まで、6次産業のことがわかる番組いろいろ!

「えび」に「海老」の字を当てるのは、ヒゲのような長い触角と曲がった腰が老人を思わせることから。「海の老人」だけに、長生きを象徴する縁起物にもなっています。とはいえ、クルマエビの寿命はわずか2年ほど。いっぽう、イセエビは20年以上生きるともいわれますから、「海老」の字がふさわしいのはやはりこちら。お正月かざりに使われるのもイセエビです。
エビのカクテル、といってもエビのお酒ではありません。英語の「カクテル(cocktail)」には「カクテルグラスに入れて出す前菜料理」の意味もあり、エビのカクテルもその一種。グラスのふちにずらりと「ひっかけ」られたゆでエビの尾をつまみ、ケチャップやマヨネーズなどをベースにしたソースにつけていただきます。はなやかなエビの赤はパーティーにぴったり。ノンアルコールでも、しっかり場を盛り上げてくれます。
おすしのネタでもおなじみの「甘エビ」は、成長すると性別が変わるという変わった特徴を持っています。卵から生まれたばかりの甘エビはすべてオス。そして体が大きくなった5才くらいからオスの甘エビはメスへと変化を始めます。甘エビが大きくなってからメスになる理由は、産卵後、卵を長期間抱き続けるには体力のある大きな体が必要だからだそうです。つまり、回転ずしのお店のカウンターでくるくると回っている甘エビは全部メスということになります。
江戸時代の歌舞伎(かぶき)役者、五代目・市川團十郎は「團十郎」の名を息子にゆずるさい、「祖父(二代目)と父(四代目)は團十郎の名をゆずった後、名を『海老蔵(えびぞう)』と改めましたが、私は『ざこ鰕(=小エビ)』の『鰕』を使うことにいたします」といって名を「鰕蔵」としたそうです。「鰕」が小エビなら「海老」はイセエビ。粋な五代目は「私など先代には遠くおよびません」という気持ちを「鰕」の一字にこめたのです。